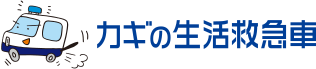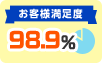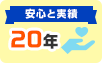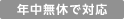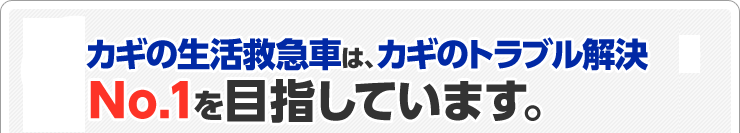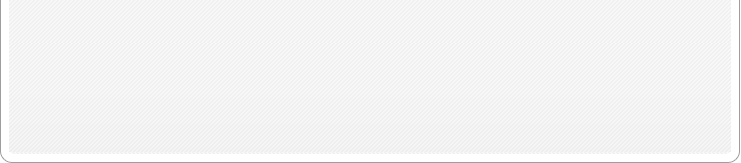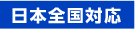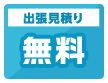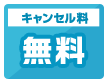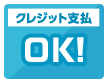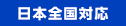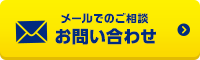カテゴリー:鍵の種類・特徴
日本国内の住宅に使用される鍵は、ほとんどが「シリンダー錠」です。 しかしシリンダー錠と一口に言っても、たくさんの分類・種類があることをご存じでしょうか? 今回は、そんなシリンダー錠の仕組みや種類、「本締錠」との違いについて解説します。
目次
シリンダー錠とは

シリンダー錠とは、鍵を差し込む本体部分(シリンダー)が、円筒状の形をしている錠全般のことを言います。 シリンダー錠の「シリンダー」は、「円筒」という意味を持っています。
シリンダー錠の仕組みとは

シリンダー錠は、錠ケースに固定されている太い「外筒」と、その中に納まっている細い「内筒」という2つの円筒で成り立っています。
鍵穴は内筒部分にあり、内筒から外筒に向けて突き抜けるような形で「タンブラー」と呼ばれる障害物が複数配置されています。
内筒にはスプリングのついた数本のピンが配置されており、ピンの配置にぴったり適合する正しい鍵を差し込んで回すことで内筒が回転し、施錠・開錠ができるという仕組みです。
シリンダー錠を室内側から施錠・開錠する際は「サムターン」と呼ばれるつまみを回すことで操作します。
シリンダー錠にはどんな種類がある?
シリーンダー錠は最も広く用いられている形態の錠前ですが、実は数種類あるのをご存知でしょうか?
ここでは、主なシリンダー錠の種類とその特色をご紹介しましょう。
ディスクシリンダータイプ
ディスクタンブラーという、シンプルな障害物を使用したシリンダー錠です。 タンブラーの形状が円盤に近い形をしているため、ディスク(円盤)シリンダー錠と呼ばれています。
ディスクシリンダータイプの鍵は、1970年代に最先端の革新的な鍵として爆発的に広まりました。 しかし2000年代初頭、外国からピッキングによって窃盗を行う犯罪集団が来日するようになって以来、ピッキングに極めて弱く安全性の低い鍵として知られることとなってしまいました。
現在はメーカーでの生産も終了しており、ディスクシリンダータイプの鍵を使用している場合は、最新式の防犯性能の高い鍵へ取り換えることが勧められています。
弊社では防犯性の高い鍵への交換を、部品代・作業代・出張費込みで10,000円〜承っております。
詳細を今すぐ知りたい方はフリーダイヤル(0120-409-020【6:00-25:00】)へお気軽にお問い合わせ下さい。
お時間ある方はお問い合わせフォームからも受け付けております。
ロータリーディスクタンブラータイプ
前述のディスクシリンダータイプよりも、防犯性を強化したものがロータリーディスクタンブラータイプです。
内筒の中の構造はディスクシリンダーより複雑です。アルファベットの「C」のような形をしたタンブラーを、ロッキングバーと呼ばれる棒状の部品でおさえることで施錠をしています。
鍵穴に正しい鍵を差し込むと、タンブラーの下部に刻まれた切り欠き部分がロッキングバーの位置にぴったりと揃います。
そして鍵を回すと、ロッキングバーが切り欠きの中に入り込むことで内筒内に収まり、内筒が回転して鍵が開くという仕組みです。
このタンブラーの回転動作を表して、「ロータリー」ディスクと呼ぶようになりました。 ロータリーディスクタンブラータイプには様々な種類があり、ピッキング耐性は種類ごとに異なります。
しかし現在の防犯基準に照らして考えると、それほど高い防犯性能は持っていないと言えるでしょう。
ピンシリンダータイプ
現在主流となっているディンプルシリンダーが登場する前に一般的な住宅の鍵として用いられていたのが、ピンシリンダータイプです。
鍵の左右どちらかにのみ、ギザギザの加工がしてあるのが特徴です。 内筒内には、ピン状のタンブラーが一直線に配列されています。このため、ピンシリンダーと呼ばれています。
現在出回っているピンシリンダー錠は、若干の改良がなされているもののやはり防犯姓は低く、危険な鍵と言えるでしょう。 構造も単純なことから、ピッキングの被害に遭いやすい脆弱なシリンダー錠であると言えます。
ピンシリンダーを使用している場合は、防犯性能の高い新しい鍵に交換するか、補助錠を取りつけるなどして対策をすることが勧められています。
マグネットタンブラーシリンダータイプ
磁石が同極同士で反発する特性を利用したシリンダー錠です。 鍵とタンブラーの双方に、磁石を使用しています。
磁石を入れた棒状のタンブラーは、外筒と内筒を貫通する形で配列されています。 ロックされている時のタンブラーはスプリングにより、内筒の方へ押し出されている状態です。 そして鍵には、適合するタンブラーの磁石と同じ極の磁石が仕込まれています。
正しい鍵を差し込むことで、タンブラーの磁石と鍵に仕込まれた磁石は反発し合います。 これによってタンブラーが外筒の方へ押し戻される形となり、鍵を回すと内筒が回転して鍵が開くという仕組みです。
ただしマグネットやスプリングの効力は経年劣化によって衰えるため、ある程度の期間使用したマグネットタンブラーシリンダー錠は鍵が差し込みづらくなったり、鍵が回らない(開錠できない)という不具合も起こります。
鍵が開かなくなってしまっては一大事です。
マグネットタンブラーシリンダー錠は不具合が起きる前に、定期的なメンテナンスを行っておくことが重要となります。
ディンプルシリンダータイプ
ピッキング被害を防ぐために、複数列のピンが多方面から配置されている、非常に防犯性能の高い鍵がディンプルシリンダータイプです。
かなりの時間をかけないとピッキングができない、非常に複雑な内部構造となっています。 現在の日本国内では、トップクラスの防犯性能を持っていると言っても過言ではないでしょう。
ディンプルキーには裏表の設定がなく、リバーシブルにどちらの面からでも差し込みが可能な点もポイントです。
また、従来の鍵のようにギザギザとした刻みがないため、服に引っかかってほつれさせてしまったり、手肌を引っ掻いてケガをしてしまったりという心配がありません。
現在では住宅だけでなく、金庫や店舗の鍵としても使用されている信頼度の高いタイプです。
シリンダー錠と本締錠の違いとは

シリンダー錠とは、円筒の中に鍵穴など施錠・開錠に必要な機構が納められている錠を指します。 鍵を差し込んで錠前を操作する「鍵穴」の部分のことをシリンダー錠と表現することもあります。
それに対し本締錠とは、デッドボルト(ストッパーとなる突出部分)だけを備えた錠で、ラッチボルトを持たない構造の錠を指しています。
ラッチボルトとは、レバーハンドルやドアノブを回した時に連動して出たり引っ込んだりする突起部分のことで、施錠していない時に風がドアに吹き付けても、閉めたドアが開かないように保持するなど、ドアを閉めた状態を維持するために必要な部分です。
デッドボルトは、施錠(本締り)するためのボルトで、別の呼び方では「かんぬき」となります。 そのため本締錠とは、施錠を目的とした錠を指しているという風にも表現することができるでしょう。
本締錠は、店舗などでは空錠と組み合わせて主錠として使用されることもあります。一般の住宅の場合は、補助錠としての使用がほとんどでしょう。
本締錠にも様々なタイプがあります。
玄関のドアノブのように扉に彫り込むタイプの本締錠と、面付と呼ばれるタイプの2種類があります。
新たに補助錠として取り付けるなら、「面付本締錠」が最適でしょう。ドアの面に対して取りつけられる錠という意味合いから、この名称で呼ばれるようになりました。
ドアの内側に取りつける面付本締錠は、ドアの外枠にデッドボルト部分が隠れることで外側からはドアが開かないようになります。 バールなどによるこじ開け被害に対し、非常に効果的な補助錠です。
しかも面付タイプは彫り込みタイプに比べ、比較的取付が容易で本体代金も安価です。 またドアの内側に取りつけるため、ピッキングやイタズラの心配がありません。
まとめ

シリンダー錠は、円筒型の機構を持つ錠前です。ディンプルシリンダー・マグネットタンブラーシリンダー・ピンシリンダーなど、色々な種類があります。
本締錠は、かんぬき部分のみを備えた錠で、おもに施錠を目的として導入される錠です。一般の住宅では、補助錠として本締錠を取りつけることが防犯対策として効果的です。